65頭の牛を襲ってきたヒグマ「OSO18」はどこにいるのか。
1. 前代未聞の被害 その全貌
「前例にないです。まるっきり」。そう語るのは、道内随一のヒグマ捕獲のエキスパート集団、NPO法人南知床・ヒグマ情報センターの理事長・藤本靖さん。道東一円から集まる凄腕のハンターたちで構成するメンバーで、これまで300頭以上のヒグマを捕獲してきた実績がある。だが、OSO18と名付けられたヒグマは、そのどのケースにも当てはまらない異常さがあると語る。「何のために襲っているのかちょっと理解できないです」
すべての始まりは、2019年7月16日、標茶町オソツベツにある牧場でのことだった。朝4時、牧場主が餌を準備していたところ、牛たちが放牧地の手前側に固まって寄っていた。普段はそんなことはないため、不審に思っていた。
そして夕方、牛が1頭足りないことに気づいた。牧場主の息子が周囲の捜索を始め、放牧地の脇を流れる沢の方へと向かった。沢に降りる斜面で見つけたのは、殺された牛の死体。そばには牛を引きずった跡と血痕が残されていた。足を滑らせ声をあげたところ、20~30m先の藪からヒグマが飛び出し逃げていった。これが、最初で最後の目撃情報となる。

400キロもある牛が森に引きずり込まれていた
それから被害は瞬く間に拡大する。8月5日に8頭、8月6日に4頭、8月11日に5頭・・・。わずか2か月のあいだに、28頭の牛が襲われた。複数の現場には、共通する痕跡が残されていた。体毛、そして、幅18cmの大型の前足の跡である。
だが、体毛分析は難航を極める。最初の年の被害現場は9つ。すべての現場で体毛が採取されたが、他の動物のものが入り交じっていて、ヒグマの体毛は4つだけ。うち2つは、状態が悪くDNAを検出できなかった。残る2つ、7月16日の現場と、9月2日の現場の体毛からDNAが検出され、同じ個体だと判明した。
採取できた2つのDNAが一致したことで、最初の2019年にも、同じヒグマが牛を襲っている可能性があるとの見立てはあった。だが、翌2020年、それは確信へ変わっていく。この年に起きた5つの被害現場で採取された体毛のDNAが、すべて、前の年に検出したDNAと同じだったのだ。
こうして、去年までに被害が起きた25の現場のうち、9か所の体毛は同一のオスグマのものであることが判明。18センチの足跡が多くの現場で見つかったことや、牛を襲う行動自体の特殊性から、すべてが一頭のヒグマの仕業によると北海道庁は断定。この正体不明のヒグマは、足のサイズと最初の被害現場オソツベツにちなみ、「OSO18」と名付けられた。

被害現場は4年間で31か所。襲われた牛は65頭にのぼる
OSO18にはいくつもの謎があった。
謎1 正体不明 目撃されない
最初の被害現場でヒグマが一度だけ目撃されていたものの、それ以降、一切目撃されていない。そして最初で最後となる一回の目撃情報も、OSO18かどうかの確証はない。間違いなくOSO18であるヒグマを目にした人が、この4年間でひとりもおらず、その身体的特徴が全くわからないのだ。
謎2 高度な学習能力 罠を見抜く
OSO18の捕獲を目指して現場付近で地元猟友会のハンターたちが仕掛けたのは、檻型の罠。中には、エゾシカの肉が入れられた。ある日、猟友会のハンターらが罠の見回りにいった時のこと。中の肉は食べられ、罠が作動し、扉が落ちていた。しかし、そこにヒグマの姿はなかった。檻の中に全身を入れず、餌だけを掻き出していたのである。OSO18は高度な知能を持ち、罠を見抜いているのではないかと、言われるようになった。
謎3 動機不明 襲った牛を食べない
全65頭の被害牛のうち、31頭は殺されることなく、ただ傷つけられただけだった。本来、ヒグマは獲物に強く執着する動物であり、一度手にした肉は土の中に隠して繰り返し食いあさる。しかし、OSO18は襲った牛に執着しないどころか、食べようとすらしないケースが約半数にのぼっており、「ハンティングを楽しんでいるのではないか」とも噂された。
「超巨大ヒグマ」「忍者グマ」「猟奇的」「怪物」・・・。いつしかOSO18は、地元住民やメディアの間で、いくつもの異名を持つようになった。
2. 見えないOSO18を導く“道”があった
目撃されないOSO18の姿。被害は直径30キロの範囲に広がり、それぞれの地点間を移動するには鉄道や国道を何度も横断せざるを得ない。にもかかわらず、なぜかOSO18は一度も目撃されることなく、襲撃を繰り返している。
私たち取材班は、約1年をかけ、全35軒に及ぶ被害を受けた酪農家の9割に聞き取り調査を行った。取材記録から浮かび上がってきたのは、異なる日に異なる場所で起きた襲撃が、極めて似た環境で発生していたということだった。
2019年8月6日に被害にあった酪農家・佐藤守さんは、被害現場の放牧地でこう証言した。
「昔はこういう風に開けた放牧地じゃなくて、木が生い茂ってて、ここは『熊の沢』って呼ばれてたんです。牛を飼うために放牧地をどんどん広げてきましたから。もともと熊のいるところを切り拓いたというか」
2021年7月1日に被害にあった酪農家・髙野政広さんは、別の被害を受けた放牧地でこう証言した。
「牛が襲われた場所から向こうの沢は、昔、別名『熊の沢』って言われてたんですよね。そばにうちの牛が夜寝てて、多分、『熊の沢』からそーっと来て、ガッと襲ったのかなと」
いくつかの異なる被害現場のすぐ脇に、「熊の沢」という共通の名を持つ沢が存在していたのだ。私たちが確認できただけでも、「熊の沢」は町内に5か所もあった。

標茶町中チャンベツにある熊の沢
北海道の開拓期、まだ人間の開発の手が今ほど入っていなかった時代、ヒグマは現在よりはるかに多く生息していたと推測されている。ヒグマが跋扈していた時代の記憶が色濃い時代に名付けられた「熊の沢」は、ヒグマが住みやすい環境がそこにあることを今に伝えていたのではないか。地図に載ることもない地元の人たち独自の呼称が、今回のOSO18の被害を予見していた可能性がある。
さらに取材を進めると、「熊の沢」に限らず、多くの被害が、川や沢のそばで発生していることがわかってきた。証言をもとに被害地点を落とし込んで、独自に制作した地図。川や沢など水路を示す線の全てを青いマーカーでなぞっていくと、関連性が見えてきた。

被害地点の多くは川や沢のそばにあった
この地域は、北海道各地にある酪農地帯の中でも、特殊な地形をしている。放牧地の隙間に、川や沢、林、湿地がモザイク状に入り組んでいるのだ。

地平線の奥まで、起伏に富んだモザイク状の景観が続いている
木々が生い茂る川をつたって歩けば、誰にも見られることなく、町中の放牧地を行き来することができる。OSO18は、人間に姿を見られないよう、沢をあえて選んで歩いているのではないか。沢を歩きながら、時を見計らって近くの牛を襲っているのではないか。私たちはそのような仮説を持つようになった。
そして今年、その仮説を裏付ける決定的な証拠が見つかることとなった。発見したのは、前述のNPO 南知床ヒグマ情報センターの理事長・藤本さん。今年から「OSO18特別対策班」に任命され、事件直後の被害現場に駆けつけ、調査を行ってきた。藤本さんは、ことし2件目の被害となった7月11日の現場と、3件目の被害となった7月18日の現場がすぐ近くで発生していることに着目していた。

青い線は藤本さんの推測したOSO18の移動ルート
このふたつの牧場は道路を隔てて隣接している。7月11日から18日の7日間のあいだに、OSO18はこの道路のどこかを横断したはずである。7月18日、事件が発覚した日の午後、藤本さんは、周囲の道路をひたすら車で走った。しかし当初、藤本さんは、足跡や草を倒した跡など、必ずあるはずのOSO18の痕跡を見つけることができなかった。そこで、もう一度、来た道を戻って、眼を凝らした。すると、思わぬ場所に痕跡が残っているのを発見することになった。それは、道路の下にあった。

足跡が残されていたのは、道路の下だった
正確にいえば、道路が小川を跨ぐ橋の下。そこに足跡が残り、周辺の草が森の奥までバタバタと倒れていたのだ。キツネやエゾシカが通るときにできるものとはまるで違い、倒れている幅は異様に太い。これは間違いなくヒグマが歩いた痕跡である。通った形跡は一頭だけ。だとすれば、OSO18に違いないと、藤本さんは確信した。
そう、道路を“渡っていた”のではなく、“くぐっていた”のである。現場間を川や沢に沿って移動し、道路に行き当たると、その橋の下をくぐった。たとえ車通りが多い国道であったとしても、橋の下を歩いていたら目撃されづらい。人間に目撃されやすい箇所を把握し、意図的に回避する行動を取っていた。
「人が普段見ないようなところをきちんと通っている。人間の裏をかくことに長けているヒグマだとわかりました。何かのきっかけでOSO18は人間を徹底的に警戒するようになってしまった。その部分については人為的なのかもしれないです」

ことしから「OSO18特別対策班」を率いる藤本靖さん
何らかのきっかけで手に入れた高度な警戒心。沢をつたって歩き、橋の下をくぐる、という習性が、「忍者グマ」の実態だったのだ。
3. 酪農地帯の暮らしへの打撃
一頭数十万円もする牛の被害額は、少なくとも2300万円に上っている。ただ、被害は牛の損失だけにはとどまらない。4頭の被害が発生した厚岸町営牧場。地域の酪農家から子牛を預かって育てる育成牧場である。預かる牛は合計1850頭。ほとんどの牛は、春から秋の間、ずっと放牧されている。しかし事件後、放牧を続けていれば再び襲撃にあう可能性があるため、半数近くの牛を牛舎に引き上げることとなった。放棄した放牧地の面積は、270ヘクタール、東京ドームで換算すると58個分。放牧している牛のすべてを牛舎で飼育することになれば、糞尿の処理や餌やりなど、労力はそれまでの何倍にもなる。本来必要ないはずのエサ代も数千万円余分にかかってくる。
「こんなことが続くと放牧地を使えませんし、これからどうやって組み立てていったら良いのかって、それが一番心配です。これからのことは、まだ見通したたないです」。(牧場長・櫻井唯博さん)
今年3月、櫻井さんは、電気柵を放牧地の周囲に張り巡らせることを決める。全長23キロ、費用はおよそ1000万円以上にのぼるが、これで囲えるのも、放牧地全体の一部。たった一頭のヒグマを巡って、膨大な対策費がつぎ込まれているのである。

全長23キロに及ぶ電気柵の設置
影響は、経済被害だけにはとどまらない。2021年に2頭の被害にあった髙野政広さんは、いつヒグマが人間を襲うようになるかわからないと、不安を募らせている。髙野さん一家は12人で暮らす大家族。孫は5人、小学生になったばかりの男の子と、小学生にも満たない4人の女の子たちは、外遊びが大好きだ。しかし、OSO18出現以後、外にいると子供たちの身に危険が及ぶのではないかと気が気でない。今は、外遊びを止めさせている。
「(子どもが)ご近所さんのところに遊びに行くってなったときに、すぐそこまでクマが来てたら自転車で行くのも怖いよなと思ってしまう」
4. 役場が背負った使命
目撃情報さえなかったOSO18。実は、去年までに撮影された写真も、あくまで被害現場の近くで撮影されたために「OSO18とみられる」だけで、確実に確かめられたわけではない。だが、被害から4年目の今年、大きな進展があった。ついに、OSO18の姿を捕らえることに成功したのだ。そこに至るまでには、標茶町役場の知られざる執念の日々があった。
釧路から北へ車でおよそ1時間。釧路川に沿った人口7200の町が標茶町である。その中心部にある標茶町役場の正面には塔が立ち、「空と大地にミルクで乾杯」と記される。標茶町は、約48000頭の乳牛を飼育する酪農の町。その役場で、OSO18対策にあたってきたのが、標茶町役場の2階にある農林課林政係である。係長の宮澤匠さんを中心に、担当職員は3名。仕事は、町内に広がる森林の管理、近年爆発的に増えて農業被害をもたらすエゾシカやカラスなどへの対策など多岐に渡る。この4年、そうした本来業務と並行しながら、OSO18対応を続けてきた。

取材を始めて間もない2月。
宮澤さんは、冬眠明けのヒグマの足跡を探していた。
宮澤さんたちの対策は、「捕獲」と「防除」の2つから成る。「捕獲」は、その名のとおり、捕らえること。地元猟友会と共同で対応し、被害が起きれば、土日も関係なくすぐに現場に駆けつけてきたが、OSO18が姿を見せることは、これまで一度もなかった。ヒグマが冬眠に入る前の初雪直後や、冬眠明けの春の残雪期には、雪上に残される足跡を、繰り返し捜索してきたが、手がかりを発見することはできなかった。一方の「防除」とは、ヒグマの侵入を妨げ、牛への被害を防ぐこと。農家や農協とも連携し、牧場に電気柵や有刺鉄線を張るほか、音や光を発して追い払う特殊機器を設置してきた。こうした対策に一定の効果があった考えられた場所もあったが、OSO18が徐々に装置を学習している可能性もあり、被害は現在も続いている。宮澤さん自身も、標茶町の酪農家のうまれ。幼い頃から牛と共に育ってきたので、襲われた人々の気持ちはよくわかるという。

「ずっと無力感を覚えてきました。OSO18の夢でうなされたこともあります」。
相次ぐ被害を受けて、問題個体「OSO18」をなんとか捕獲したいと願ってきた宮澤さんたちには、悩みがあった。「ヒグマを殺すな」という批判のメールや電話が、度々寄せられてきたことだ。「人間が自然を開発し、野生動物のテリトリーを侵食してきた。殺すべきではない」「せめて捕獲して山奥に帰すべきだ」というのである。去年、札幌市中心部にヒグマが出没し、市民が襲われたときにも、札幌市に同様の意見が寄せられた。宮澤さんは、そうした意見を受け止めつつ、OSO18は被害の深刻さからいって、一刻も早く対処しなければならない問題個体だとして、こう話す。
「僕たちも、むやみにヒグマを駆除したいと思っているわけではありません。被害をもたらす問題個体に限りたいと考えています。OSO18だけは、放置しておくわけにいかないのです」
5. ついに見えてきたOSO18の姿
4年目の今年、宮澤さんたちは、OSO18の姿を新たな対応に乗り出していた。それが「ヘアトラップ」作戦。ヒグマには、立ち上がって木に背中をこすりつける「背こすり」と呼ばれる行動がある。この習性をいかして、木に有刺鉄線を巻いてヒグマの体毛(ヘア)を採取し、その様子を自動撮影カメラで姿を捉えようというもの。体毛からDNAを検出し、OSO18だと確かめることができれば、外見的特徴を明確につかむことができる。複数の場所で成功すれば、連続的な行動の把握につなげることも可能だ。標茶町のアドバイザーに就任した山中正実博士が、ヒグマ研究の先進地・知床で行ってきた学術調査の手法で、宮澤さんたちは、山中博士の助言に従い、「背こすり」しやすいミズナラやハルニレの木など、町内15か所にトラップを設置してきた。

4人がかりで木に有刺鉄線を巻きつける。危険があるため、作業は常に複数で行う。
設置作業に同行させてもらって、すぐに気づいたことがあった。とにかく、一つひとつが困難なのだ。前述したように、OSO18は、牧場のあいだを縫うように流れる、木立に囲まれた沢沿いに移動していると考えられた。だが、OSO18の姿を捉えるためには、まさにそうした沢に分け入る必要がある。草が生い茂る泥濘(ぬかるみ)を進み、ヒグマが好む木を見つけて有刺鉄線を巻き、誘き寄せるための防腐剤をかける。そばには、ヒグマの大きさの目安となるポールを立てる。そして、その2つの木を見渡せる位置にある木に、センサーつきの自動撮影カメラをくくりつける。
そうした条件が整う環境は、少ない。やっと見つけたと思ったら、周りの草を刈り払わなければならないことも多く、一つの現場に2時間かかることもある。茂みのなかから、いつヒグマが現れてもおかしくないため、熊鈴と熊スプレーは手放すことができない。とりわけ危険度が高い現場には、ハンターである職員が銃を携行する。
設置すれば終わりではなかった。動きや温度に反応する自動撮影カメラには、撮影するとメールで知らせてくれる機能が付いているものもあるが、設置場所の多くが圏外。定期的に足を運んで見回りを続け、体毛を採取しなければならない。複数のヒグマが背こすりをしている可能性もあるため、こまめに通う必要があった。宮澤さんたちは、こうした一連の作業を、淡々と続けていた。
私たちが宮澤さんに話を聞いたのは、10月に入ってからだった。
「ついに、OSO18の姿を捉えました」。
標茶町チャンベツに設置した有刺鉄線から採取されたヒグマの体毛から、ついにOSO18のDNAが採取されたという。同時に映像も撮影されていた。
だが、その映像は、夜間のため、非常に見にくい。役場から映像を託された私たちは、AIによる解析で実績のある外部企業と連携し、映像の鮮明化を行った。ノイズを除去し、ヒグマや草木の画像データを、AIに学習させる。すると、判別しにくかった部分が、徐々にはっきりとしてきた。

元の画像

鮮明化した画像
赤外線をつかった自動撮影カメラで、夜間撮影を行うと、二種類のノイズが発生する。一つは、夜間の撮影で光量が少ないために生じるショットノイズ、もう一つは被写体の動きによって生じるモーションブラーノイズである。この2つのノイズを除去するために、AIを使う。少し詳しく解説しよう。まず、ある画像に、あえてノイズを載せる。このとき、ノイズを載せた「きたない画像」から、元になっている「きれいな画像」を出力するためのアルゴリズムをはじき出す。これを、画像30000枚分繰り返すと、「きたない画像」から「きれいな画像」が出力されるための一般的なアルゴリズムが導き出せる。こうしたアルゴリズムを、今回、ショットノイズ、モーションブラーノイズそれぞれを除去するために、使用した。また、モーションブラーノイズについては、白黒画像ではノイズ除去が難しかったため、その前段で、AIを使ったカラー化も行った。ヒグマや草木などが映った45000枚のカラー画像を学習し、自動着色したのだ。さらに、そうしてノイズを除去した画像の、高解像化も行った。「超解像」と呼ばれる手法で、粗い画像の高解像化を行うアルゴリズムを、学習データから導き出し、それを使用した。
まとめると、①元の画像→②ショットノイズ除去→③自動着色によるカラー化→④モーションブラーノイズ除去→⑤超解像という流れになる。それぞれの段階の画像が下記になる。厳密にいえば、学習データとのズレによって、これが、間違いなく実物の姿だとは言えないが、姿を見せなかったOSO18の姿と輪郭が、はっきりと浮かび上がってきた。



6. 野生の大逆襲
北海道において、ヒグマの立場は、紆余曲折をたどってきた。今では信じにくいことだが、戦後のある時期まで、北海道は長くヒグマを根絶させようとする政策をとっていた。とりわけ、1966年に始まった「春グマ駆除」(冬眠明けのヒグマが雪上に残す足跡を追って捕獲する)は、絶大な効果をあげて、一時、ヒグマは絶滅を危惧されるまでに減った。変化のきっかけは、生物多様性を求める声が高まったこと。1989年にカナダで開かれた第8回国際クマ会議で、「日本はクマの駆除と生息域破壊を続け、保護政策に関して無策」と、国際自然保護連合(IUCN)から指摘を受けたことも影響し、1990年、道庁は「春グマ駆除」の禁止に踏み切った。
だが、高度成長期以降、若者が都市へ移動し、ハンターが高齢化していたことで狩猟文化が廃れつつあった北海道で、「春グマ駆除」の禁止は大きな影響があった。ヒグマを撃てる猟師の減少だ。かつては、標茶町にも「名人」と呼ばれる熊撃ちがいた。だが、捕獲の機会が激減し、技術が継承されず、地元猟友会のなかにヒグマを撃った経験があるハンターが少なくなっていた。そのため、森に分け入り、居場所のわからない「OSO18」を捜索し、発見すれば捕獲する、きわめて危険な任務を担うことができなくなっているのだ。
「OSO18」に象徴されるように、いま、人間とヒグマの関係は大きく変貌している。2021年度は、ヒグマによる人身被害が9件14人となり、統計を取り始めた1962年以来、過去最多。とりわけ、去年6月に、200万都市札幌の中心部へ出没したことは、大きな衝撃を与えた。ヒグマによる被害が全道で増えるこの状況を、北海道庁の鳥獣行政担当者は「時代が大きく変わろうとしている」と表現。長年ヒグマの生態を調査してきた研究者は「野生の大逆襲だ」と語る。
この大逆襲にどう対峙していくのか、OSO18 は、そんな問いを人間に投げかけている。
凶暴ヒグマ「OSO18」の熊肉、ネット通販で大人気 売り切れ続出 再販の予定は?
標茶町や厚岸町でOSO包囲網が敷かれる中、7月30日に釧路町で1頭のヒグマが捕獲されました。 当初は普通のクマと思われていましたが、その後のDNA鑑定で「OSO18」だったことが8月22日に明らかにされました。

車と比較するとかなりの大きさであることがわかる(提供:加工業者)
その「OSO18」、駆除されたあとは肉として加工され、ジビエとして東京や北海道内の飲食店で提供されていたことが分かりました。 精肉加工をした白糠町の業者によりますと「OSO18」は駆除された7月30日にハンターによって持ち込まれ、解体されたということです。

内臓を除く状態で体重304キロ (提供:加工業者)
体重は内臓を除いた状態で304キロで、クマの中では大きい部類でした。ただ痩せ気味で脂は比較的少なかったということです。 加工した業者は「まさかOSO18だとは思わなかった。毛が短いクマだった」と驚いた様子で話していました。

OSO18 (6月25日 提供:標茶町)
肉はすでに東京都内のジビエ料理店に売られ、すでに”熊肉”として提供されているほか、8月24日夜には、釧路市内の飲食店でも振る舞われる予定です。
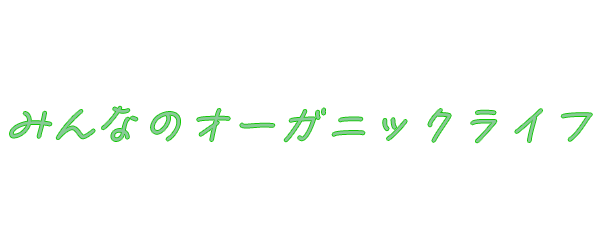



















コメント